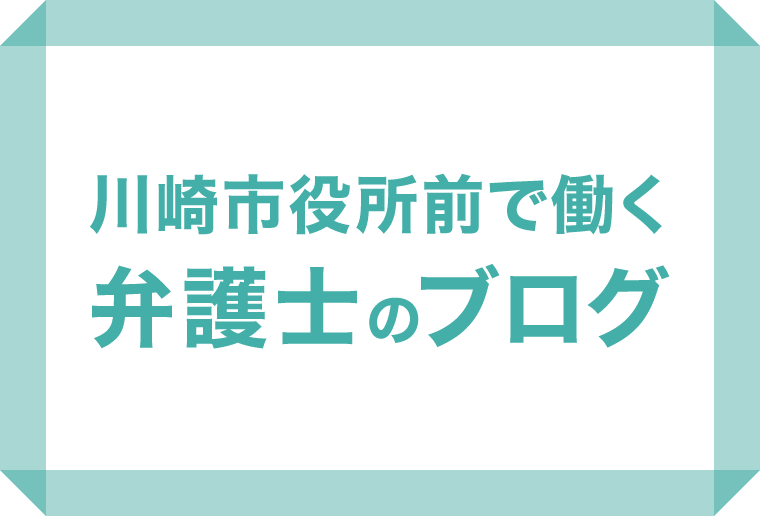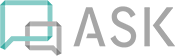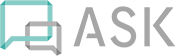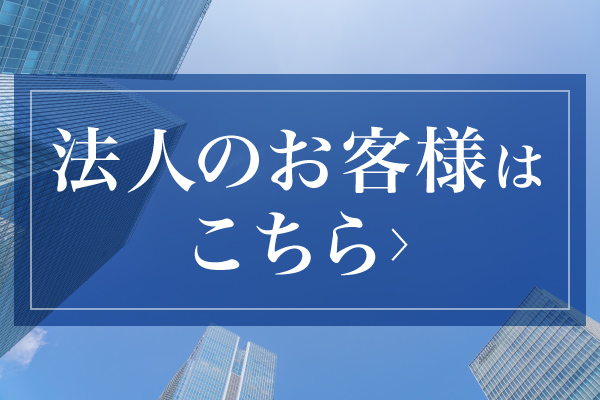川崎(じもと)の弁護士 伊藤諭 です。 先日,当事務所の竹内と共に顧問企業様にお邪魔して,簡単な勉強会を開催しました。  テーマは「債権回収」 ビジネスはお金を回収するまでが大事です。 まず気をつけたいのが,時効の管理。 債権(請求できる権利)はその権利を行使できるときから一定期間経過すると,時効になってしまいます。 つまり,一定期間経過した債権については,権利の相手方が「時効を援用します(時効の恩恵を享受します)」と主張した ら,それ以上権利の行使ができなくなってしまうのです。 問題は「一定期間」がどの程度の期間かということです。 原則 個人間の貸し借りなどの場合,原則は10年です。 商人(株式会社など)の行為が原因の権利については,原則5年になります。 しかし,これはあくまでも原則。 法律では,それより短い期間で時効となってしまう権利がいろいろあります。 ① 商品売買代金債権 「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」については,2年(民法173条1号)で時効になります。 日常的にお店で買い物した代金は,2年で時効になるんですね。 ② 請負代金債権(工事・設計・監理) 「工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権」については,工事が終了したときから3年(民法170条2号)で時効です。 ③ 動産の賃貸借 「動産の損料に係る債権」については1年(民法174条5号)とより短くなっております。 但し,数ヶ月間にわたり,賃料毎月払いの約定で賃借された土木建設用の機械であるショベルドーザーの賃料については商事債権として5年とする判例あり ② その他商事債権 5年(商法522条) 2.消滅時効の起算点 権利を行使することができる時から進行(民法166条1項) →通常は弁済期から進行する。 3.時効の中断について(民法147条) ① 弁済を受ける→少額でも入金をしてもらう。 ② 債務の承認をしてもらう→日付・署名・押印 ③ 請求する。 但し,6ヶ月以内に訴訟提起,支払督促,調停申し立て等の法的措置を執らなければ中断の効力は生じない(民法153条) 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
テーマは「債権回収」 ビジネスはお金を回収するまでが大事です。 まず気をつけたいのが,時効の管理。 債権(請求できる権利)はその権利を行使できるときから一定期間経過すると,時効になってしまいます。 つまり,一定期間経過した債権については,権利の相手方が「時効を援用します(時効の恩恵を享受します)」と主張した ら,それ以上権利の行使ができなくなってしまうのです。 問題は「一定期間」がどの程度の期間かということです。 原則 個人間の貸し借りなどの場合,原則は10年です。 商人(株式会社など)の行為が原因の権利については,原則5年になります。 しかし,これはあくまでも原則。 法律では,それより短い期間で時効となってしまう権利がいろいろあります。 ① 商品売買代金債権 「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」については,2年(民法173条1号)で時効になります。 日常的にお店で買い物した代金は,2年で時効になるんですね。 ② 請負代金債権(工事・設計・監理) 「工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権」については,工事が終了したときから3年(民法170条2号)で時効です。 ③ 動産の賃貸借 「動産の損料に係る債権」については1年(民法174条5号)とより短くなっております。 但し,数ヶ月間にわたり,賃料毎月払いの約定で賃借された土木建設用の機械であるショベルドーザーの賃料については商事債権として5年とする判例あり ② その他商事債権 5年(商法522条) 2.消滅時効の起算点 権利を行使することができる時から進行(民法166条1項) →通常は弁済期から進行する。 3.時効の中断について(民法147条) ① 弁済を受ける→少額でも入金をしてもらう。 ② 債務の承認をしてもらう→日付・署名・押印 ③ 請求する。 但し,6ヶ月以内に訴訟提起,支払督促,調停申し立て等の法的措置を執らなければ中断の効力は生じない(民法153条) 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
ブログ
10view
時効にご用心!債権管理の基本のキ