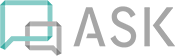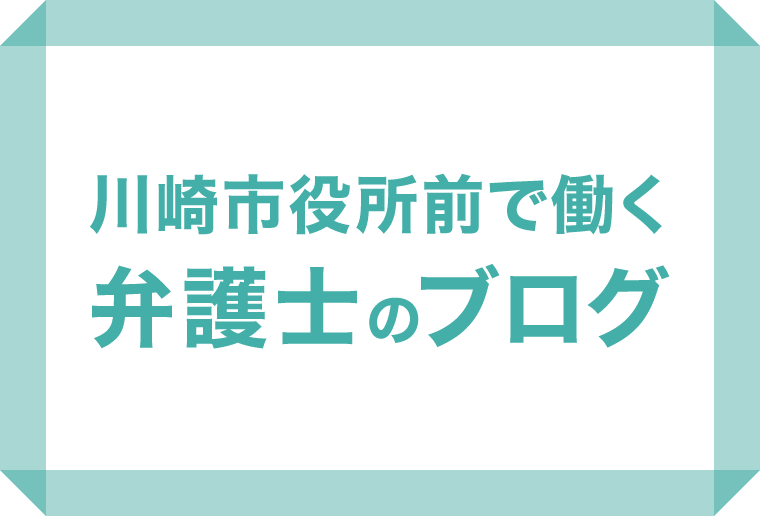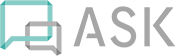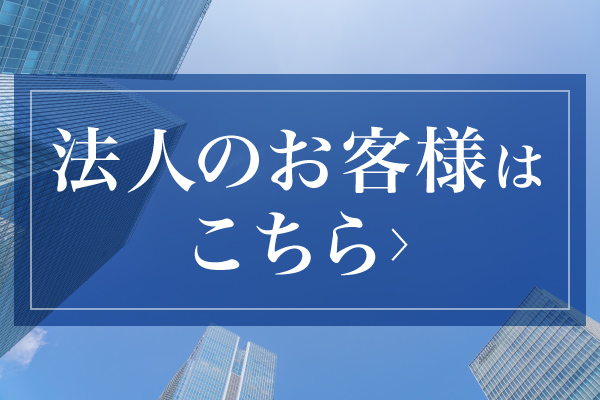川崎(じもと)の弁護士 伊藤諭 です。 先日,横浜弁護士会が若手育成のために始めたチューター制度の企画で,新人弁護士の方々との飲み会勉強会に参加してきました。 そこでのテーマが「二段の推定」。 みなさん,契約書や申込書その他大事そうな書類に印鑑を要求されますよね? どうしてこんなことを求められるのか。 それは,日本はハンコ社会だから。 ハンコの押してある文書というのは,他の書面より信用できるからなんです。 しかも,これは単なる慣習を超えて,法律上の理由もあるんですね。 ハンコが押してある文書というのは,その人が作った文書であると推定しましょう。違うというのであれば,違うということを証明しなさい,というルールになっています。 もっときちんと説明すると,  よく裁判で問題になるのは,この文書(たとえば契約書)が偽造されたものかどうかということです。 A株式会社が,金銭消費貸借契約(お金を貸すという契約)に基づいて甲野太郎さんに貸したお金の返済を求める裁判を起こしました。甲野太郎さんはまったく身に覚えがないということで争っています。 A株式会社は,甲野太郎さんの署名とハンコが押してある契約書を証拠で出してきました。 A株式会社は,このハンコが甲野太郎さんのものであるということさえ証明すれば,このハンコが甲野さんが押したものだと推定され(これは判例で認められたルールです),甲野さんが押したものであれば,甲野さんがこの文書を作ったものだと推定されることになります(これは民事訴訟法上のルールです。)。 この2つの推定が「二段の推定」です。 A株式会社は,甲野さんの印鑑証明書を出して,これが甲野さんのハンコだということを証明してきました。これだけで,二段の推定によって,この契約書が真正なもの(甲野さんの意思に沿った文書であること)が推定できることになります。 そうなると甲野さんは,この2つの推定のどこかをくずさないと負けてしまいます。 甲野さんは,自分のハンコだけれども自分が押したのではない(①の推定を破る反論)とか,自分が押したのだとしても,自分の意思を示した文書を作成したものではない(②の推定を破る反論)ということを具体的に証明していく必要があります。 少し考えていただければわかるように,この反論は相当難しいものです。 甲野さんの敗色は濃厚といったところでしょう。 先日の勉強会では違う方向に議論が膨らんでいったのですが,ここでは言えませんw 今日の一言
よく裁判で問題になるのは,この文書(たとえば契約書)が偽造されたものかどうかということです。 A株式会社が,金銭消費貸借契約(お金を貸すという契約)に基づいて甲野太郎さんに貸したお金の返済を求める裁判を起こしました。甲野太郎さんはまったく身に覚えがないということで争っています。 A株式会社は,甲野太郎さんの署名とハンコが押してある契約書を証拠で出してきました。 A株式会社は,このハンコが甲野太郎さんのものであるということさえ証明すれば,このハンコが甲野さんが押したものだと推定され(これは判例で認められたルールです),甲野さんが押したものであれば,甲野さんがこの文書を作ったものだと推定されることになります(これは民事訴訟法上のルールです。)。 この2つの推定が「二段の推定」です。 A株式会社は,甲野さんの印鑑証明書を出して,これが甲野さんのハンコだということを証明してきました。これだけで,二段の推定によって,この契約書が真正なもの(甲野さんの意思に沿った文書であること)が推定できることになります。 そうなると甲野さんは,この2つの推定のどこかをくずさないと負けてしまいます。 甲野さんは,自分のハンコだけれども自分が押したのではない(①の推定を破る反論)とか,自分が押したのだとしても,自分の意思を示した文書を作成したものではない(②の推定を破る反論)ということを具体的に証明していく必要があります。 少し考えていただければわかるように,この反論は相当難しいものです。 甲野さんの敗色は濃厚といったところでしょう。 先日の勉強会では違う方向に議論が膨らんでいったのですが,ここでは言えませんw 今日の一言
ハンコを押すのは慎重に