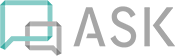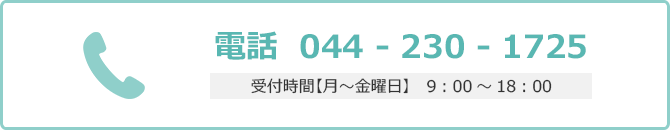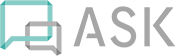法定相続分については、すでに見てきました。
「私は、お父さんの面倒をこんなに見てきたのに!」
「弟はむかしから、死んだ親父からいろんな施しを受けていたはずだ!』
法定相続分では公平な遺産分割ができない場合に、相続人の間でその調整をするのが「寄与分」、「特別受益」の制度です。
寄与分=遺産への貢献
亡くなった方が遺言を残していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議をすることとなりますが、法律で法定相続分が定められているので、法定相続分に応じて遺産を分配することが多いでしょう。
しかし亡くなった方の遺産の増加に貢献をしたり、または遺産が減少するのを防止したりしたのに、その貢献が反映されないというのはさびしいですし、貢献が遺産分割に反映されないと不公平な気がします。
そこで法律は、遺産の増加に貢献したり、減少の防止をした法定相続人に、「寄与分」として寄与した分を多めに相続する制度を設けています(民法904条の2)。
寄与の程度を金銭評価したうえで、遺産の中から「寄与分」をまずはじめに寄与した方に渡し、寄与分を除いた残りの財産を法定相続人全員で分配することとなります。
寄与分が認められるためには?
それでは、具体的にどんなときに寄与分が認められるのか見ていきましょう。
法定相続人であること
民法904条の2に定められている「寄与分」は、あくまでも法定相続人の中でどうやって遺産を分けるのが実質的に公平なのか、という観点から認められたものです。
したがって、「寄与分」の主張ができる人は、亡くなった方の法定相続人に限られます。
同じ「寄与」という言葉を使っているので混乱してしまうかもしれませんが、2019年7月1日に新しく施行される「特別寄与料」(民法1050条)とは異なります。「特別寄与料」は、法定相続人の親族に認められた新しい制度です。
こちらのページをご参照ください。
寄与行為が「特別」であること
先ほどお話しした「特別寄与料」と言葉が同じなので本当に紛らわしいですね。
ここでお伝えしたいことは、「通常の範囲を超えて貢献する必要がある」ということです。
夫婦間や親族間の情や扶養の範囲内の行為では寄与分は認められません。
病院にお見舞いに行ったとか、よく話し相手になったなどと言って寄与分を主張する方がいますが、この程度では寄与分までは認められません。
生前の行為であること
亡くなった後にいろいろと葬儀などの手配をしたなどの行為は寄与分とはなりません。
対価を受けていないこと(無償性)
寄与に対して対価を受けていれば、既にその対価で寄与の清算が終わっているので寄与分は認められません。
ただし、寄与に対して少々の心付けがあった程度では「対価」といえない場合もあるでしょう。
寄与によって財産が増加・維持し,または減少が食い止められたこと
寄与分は、亡くなった方の財産の増加・維持に対しての貢献でないと認められません。特別に優しくしてあげても、それが財産の増加・維持と無関係であれば「寄与分」としては評価されません。
具体的にどのような場合に寄与分が認められる?
実際にどのような場合に寄与分の主張が認められるでしょうか。
たとえば、給料をもらわずに家業を継続的に手伝ってきた、ご自身の財産を贈与した、などがわかりやすいですね。
最近特に多くなっているのが、扶養型と療養看護型です。
扶養型とは
親を引き取って長期間同居し、親の生活費を肩代わりしてきたなどが典型的です。単に同居していただけで、お互い生活費はそれぞれが負担していた場合では特別の寄与とはなりません。また短期間でも特別の寄与とは評価されません。
療養看護型とは
親と同居して親の在宅介護を長期間行っていた場合が典型です。
ただ、単に高齢に伴って手助けをしていただけでは、扶養の範囲であり、特別の寄与とは言えません。
常時、食事・排泄等の介助をしなければならず、通常ならプロに有償で依頼するようなことを、相続人が自ら継続的にしていた場合に特別の寄与と認められます。
むずかしいのは寄与分をお金としてどのように評価するかということでしょう。
本来なら看護人を雇って支払うべき対価を支払わずに済んだ分、財産の減少を免れたといえます。
その支出を免れた分を寄与として評価しようということになると思います。
ただし、介護保険制度で介護を受けていた場合には、既に介護保険でまかなわれていることになりますので,重複して介護したからといって、それだけでは寄与分は認められません。
特別受益=相続の先渡し
逆に、亡くなる前に一部の法定相続人に対してだけ財産を与えていた場合には、かかる財産の先渡しを相続の際に反映させないとまた不公平となります。
そこで法律は、一定の贈与については相続の先渡しとして考慮することとしました。
具体的には、今ある遺産に過去に贈与でもらった財産をプラスしたうえで、当該財産を元に法定相続分の金額を算定して、贈与でもらった分を既に相続として受け取ったものとして扱おうということにしました。
これを「特別受益」といいます(民法903条)。
特別受益になるもの,ならないもの
高等教育
よくあるのが、1人だけ大学にいかせてもらった,1人だけ医学部にいった,1人だけ大学院にいった,という場合です。
親の資力から分不相応な高等教育を受けていたような場合でなければ、扶養の範囲ですので特別受益にはあたりません。
逆に分不相応な高等教育であれば、分不相応な学費分が特別受益となるでしょう。
経済的援助
一部の兄弟姉妹にだけ、親がお金を贈与していた場合には、不公平ですので特別受益として考慮することになります。
ただし、扶養の範囲内の贈与の場合には、相続の先渡しとはいえないので特別受益となりません。
借地権の設定
親の所有の土地について親と借地契約を結んでその土地上に建物を建てて、親に地代を払っていた場合には、借地権をもらったこととなるので特別受益となります。
無償で土地を利用していた場合も無償の土地利用権分(使用貸借)が特別受益となります。
生命保険金
厳密にいうと生命保険はお亡くなりになって発生するので相続の先渡しとはいえませんが、保険金が出た場合に特別受益が問題となることがあります。
原則は生命保険金は亡くなった方と保険会社の契約によって受取人が保険金を受け取るので、遺産ではなく、特別受益にもなりません。
ただし、生前多額の保険料の支払いがなされ、この生命保険金とその他の遺産との額を比較してあまりに保険金が高い場合には、例外的に特別受益となる余地があります(遺産はほとんどなかったのに、生命保険がたんまり特定の人にかけてあったという場合です。)。
死亡退職金
生命保険と同じく、死亡保険金もお亡くなりになって発生するので相続の先渡しとはいえませんが、特別受益が問題となります。
本来、死亡退職金は遺族の生活保障のお金であり、会社の退職金規程に基づいて支給されるのですから、遺産にもならず特別受益にもならないのが原則です。
ただし、生命保険と同じく、当該死亡退職金とその他の遺産との額を比較してあまりに退職金が高い場合には、例外的に特別受益となることがあります。
持ち戻し免除の意思表示
持ち戻し免除の意思表示とは、「相続の先渡しとして扱わなくていいよ」と亡くなった方が言っていたよということです。
この場合には,特別受益にはあたったとしても、相続で調整しなくてよくなります。
明確なのが、遺言や手紙などはっきりと形に残っている場合です。この場合には争いにもなりにくいので、もし持ち戻し免除の気持ちがある(相続で調整して欲しくない)のであれば、遺言等で残しておくべきです。
ただ、通常、特別受益が問題となるのは、遺言がなく、法定相続人間で遺産分割をしなければならない場面なので、書面等で持ち戻し免除の意思表示がなされていることは多くありません。
だからといって書面で残っていなければ持ち戻し免除の意思表示が認められないかというとそうではなく、「相続の先渡しとして扱わなくていいよ」と親が思っていたに違いない、思っていたはずだ、という状況の場合、親の気持ちを汲んで「黙示の持ち戻し免除の意思表示」があったと扱います。
たとえば土地の利用に関して、親と同居して暮らすための場合には、土地の利用権に関して特別受益にあたっても、持ち戻し免除の意思表示が見られる場合が多いでしょう。
また高等教育については全員が同程度の教育を受けていたのであれば、親としては、相続として問題にしたいとは思っていないはずです。
ですので特別受益になったとしても、持ち戻し免除の意思表示がある場合、もしくは推定される場合には、実際の相続で取り分が減らされずに済むこととなります。
なお、相続法の改正により、婚姻期間20年以上の夫婦の間で自宅不動産の贈与があった場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定しますので、これについては調整する必要がないというのが原則になります。
実際に主張する前に
寄与分と特別受益についてだいたいおわかりいただけかと思います。
でも,
具体的にご自身に当てはまるかどうかわからない、
あてはまると思うけれど自分自身できちんと説明できるか不安だ、
という方もいらっしゃると思います。
まずは,お気軽に弁護士にご相談ください。
一緒に良い方法を考えていきましょう。
条文
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
第九章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。