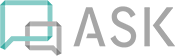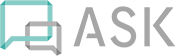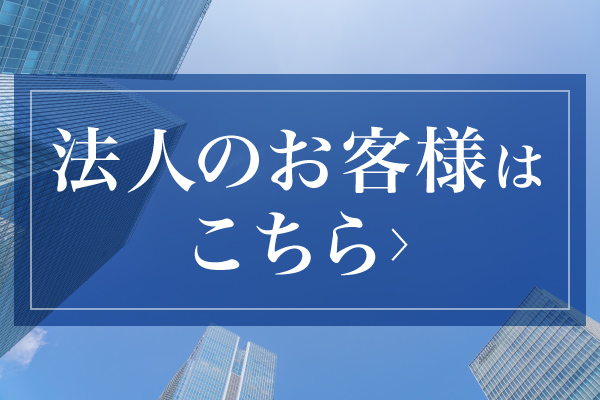インターネットを介して提供されるサービスは今や不可欠な存在です。
今の生活において、ECサイトでの買い物はもちろん、サブスクサイトでの動画視聴、AIの普及による課題解決など、生活を便利にするものから企業や自治体の活動などに影響を与えるものまで、ミクロマクロを問わず、インターネット経由によるサービスは必要不可欠なものとなっています。
SNSもそのひとつですが・・・
その一端として、旧友と交流したり趣味を同じくする人たちと繋がったり、営業活動に利用したり、情報収集に利用したりと、さまざまな目的で利用する「SNS」(X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、mixi2など)があります。そんな身近なSNSですが、身近であるがゆえか匿名で利用できるがゆえか、誹謗中傷や名誉毀損的投稿が問題となることもあります。有名人の名誉を毀損するような投稿がなされ、それに対して法的措置をとったことがニュースになるといった話は、皆さんも一度ならず目にしたことがあるかと思います。
SNSにまつわるトラブルの中にはこういった点が問題になることがあります。
今回は、そのSNS利用において、なりすまし投稿の被害に遭ったと主張するアカウントの持主が、なりすまし投稿をした人間に対して法的措置を執る前提として、その者を特定するために必要な手続を行う中で、アクセスプロバイダに対して、ログイン情報の開示を求めた事案の最高裁判決を取り上げます。
事案の概要
本件は、被上告人(一審原告)が、自身のInstagramアカウントでなりすまし被害を受けたとして、そのなりすまし投稿をした者を特定するため、インターネット接続サービスを提供した経由プロバイダ(=アクセスプロバイダ)である上告人(一審被告・NTTドコモ)に対して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称、プロバイダ責任制限法)に基づいて、計8回のログインに係る情報の開示を求めた事案です。
前提知識
一般に、インターネット上で、例えば名誉毀損に当たる表現を行った場合、民事上の損害賠償責任や名誉毀損として刑事罰を受ける可能性があります。他方、その被害を受けた側としては、民事上、名誉毀損に当たる表現を行った者を相手として、その賠償を求めていくことになります。
とはいえ、名誉毀損に当たる表現を行った者は、インターネットの海を漂っている匿名の人間ですので、その投稿者を特定する必要があります。そこで、プロバイダ責任制限法に基づいて発信者情報開示の手続を行うことになります。
【プロバイダ責任制限法の改正】
プロバイダ責任制限法は、令和3年に法改正があり、その改正法が令和4年10月1日から施行されました。
【改正前の規定の概要】
インターネット上において、自己の権利を侵害されたとする者は、所定の要件を満たす場合、プロバイダ等に対して、当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができる旨規定されていました(改正前同法4条1項)。
【改正後の規定の概要】
改正後同法5条3項、同法施行規則5条は、「特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信」(ログイン通信等)のうち、一定の範囲のものを「侵害関連通信」と規定しています。
その上で、インターネット上で自己の権利を侵害されたとする者は、所定の要件を満たす場合、プロバイダ等に対して、自己の権利の侵害に係る発信者情報(侵害関連通信に係るIPアドレス等である特定発信者情報を含む)の開示を請求することができます(同法5条1項、同法施行規則2条、3条)。
また、アクセスプロバイダ等に対して侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる旨も規定され(同法5条2項)、改正により、開示請求をすることのできる情報の範囲が整理されました。
(発信者情報の開示請求)
第五条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
(1)当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所
(2)当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報
ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。
2 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。
一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
3 前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。
本事案の時系列
• 令和3年4月29日:Instagram上で氏名不詳者によるなりすまし投稿(社会生活上受忍すべき限度を超えた原告の人格的利益を侵害しり内容の投稿)
• この間、2回ログインのための通信がなされたが、NTTドコモは、自らが保有する通信記録の中から、このログインに対応するものを特定できなかった。
• 同年5月20日:ログイン①、②
• 同月22日:ログイン③、④
• 同月25日:ログイン⑦
• 同年6月13日:ログイン⑧
• 被告は、上記各ログインに係るIPアドレス接続日時にそのIPアドレスを割り当てられた電気通信設備の各日時における契約者に関する情報等を保有している。
• 令和4年10月1日 一部改正されたプロバイダ責任制限法が施行
• 令和5年2月 大阪高裁での弁論が終結した。
裁判所の判断
原審の判断
Ø 本件請求については、改正前法4条1項の規定が適用される。
Ø 本件各ログインと本件各投稿をした者が同一人であることからすれば、本件各情報は同項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に当たる。
⇒一審原告は、一審被告に対して本件各情報の開示を請求することができると判断し、ログイン①〜⑧について情報開示を認めました。
最高裁の判断
しかし、最高裁は、上記原審とは異なり、次のように判断して、ログイン①のみの開示を認めました。
法改正による適用条文の選択について
Ø 令和3年改正法附則には、改正前法4条2項の規定による意見の聴取を改正後法6条1項の規定によりされた意見の聴取とみなす旨の定めがあるものの(2条)、令和3年改正法その他の法令において、そのほかに、権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年改正法の施行前にされた場合について、改正後法の規定の適用を排除し、改正前法の定めるところによる旨の経過措置等の規定が置かれていないこと
Ø 令和3年改正法は、改正後法5条において、発信者情報の開示請求権の要件を一部整理するなどしたものであって、発信者情報の開示請求権そのものを新たに創設したものではないこと
⇒よって、改正後法5条2項の規定は、権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年改正法の施行前にされたものである場合にも適用されると解するのが相当である。
本件各ログイン(ログイン①〜⑧)の「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの(同法施行規則5条柱書き)」該当性について
まず、前提として、本件各ログインが、同法施行規則5条2号に掲げる符号の電気通信による送信に当たることは認められています。そこで、同条柱書きの「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」といえるかどうかが問題となります。
仮に、これに当たるとすれば、ログイン①〜⑧は、侵害関連通信として、開示の対象になるということになります。
【改正後法5条1項、2項の趣旨】
侵害情報の発信者の特定のためには当該侵害情報の送信に係る発信者情報の開示を認めるのが最も適切であると考えられるものの、これにより当該発信者を特定することができない場合にログイン通信等に係る情報の開示を求めることができないとすれば侵害情報の流通により権利を侵害された被害者の救済が不十分になる一方で、ログイン通信等それ自体は権利侵害性を有しないことから、被害者の権利救済の必要性と通信者等のプライバシー、表現の自由及び通信の秘密との均衡を踏まえた要件の下で、被害者が侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる旨を明示的に規定したもの。
【改正後法5条3項の趣旨とその委任を受けた総務省令の趣旨、解釈】
上記のような趣旨を受け、同項は、開示請求の対象範囲を画する侵害関連通信について、侵害情報の発信者が行った当該侵害情報の送信に係るログイン通信等であって、当該「侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるもの」としてその具体的内容を総務省令に委任しているものと考えられ、これを受けた施行規則5条柱書きは、侵害関連通信について、同条各号に掲げる電気通信による送信であって、それぞれ「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」としている。
施行規則5条柱書きの上記文言や被害者の権利救済のために侵害関連通信に係る発信者情報の開示請求権を規定した改正後法の趣旨に照らせば、少なくとも他のログイン通信等に係る情報により侵害情報の発信者を特定できない場合にまで、侵害情報の送信との間に一定の時間的間隔があるなど当該送信との関連性を低下させ得る事情があることを理由として、一律に「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」といえないと解することは相当でない。
他方、ログイン通信等は、それが侵害情報の発信者によって行われたものであるとしても、それ自体に権利侵害性はない上、開示対象となる情報の内容は、通信がされた時期や通信に利用された機器等によって異なることがあり、通信の時間・場所など当該発信者の行動等まで推知させる情報や、当該発信者が利用したインターネット接続サービスに関する契約を締結している第三者の情報等も含み得るから、その開示によりこれらの者の権利利益が制約されることは否定できない。そして、上記の制約の程度は、開示の対象となるログイン通信等の数が増加するに従ってより大きなものとなる一方で、被害者においては、ログイン通信等のうちの一つに係る情報により侵害情報の発信者を特定できるのであれば、更にその余のログイン通信等に係る情報の開示を求める必要性があるということはできない。
【施行規則5条柱書きの「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」についての解釈と規範】
同条各号に掲げる符号の電気通信による送信それぞれについて、開示される情報が侵害情報の発信者を特定するために必要な限度のものとなるように、個々のログイン通信等と侵害情報の送信との関連性の程度と当該ログイン通信等に係る情報の開示を求める必要性とを勘案して侵害関連通信に当たるものを限定すべきことを規定したものであると解される。
そして、上記各送信のうち、施行規則5条2号に掲げる符号の電気通信による送信(以下「ログイン通信」という。)についてみれば、時間的近接性以外に個々のログイン通信と侵害情報の送信との関連性の程度を示す事情が明らかでない場合が多いものと考えられるところ、そのような場合には、少なくとも侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信が「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たり、それ以外のログイン通信は、あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情があるときにこれに当たり得るものというべきである。
当てはめ
本件について、本件投稿内容との関係でみると、これらの投稿と本件各ログインとの関連性の程度を示す事情は両者の時間的近接性以外にうかがわれないところ、本件各ログインの中では、本件投稿の21日後にされた本件ログイン①が、これらの投稿と最も時間的に近接する。
また、本件投稿と本件ログイン①との間には本件介在ログインが存在するが、上告人は自らが保有する通信記録の中から本件介在ログインに対応するものを特定できておらず、本件介在ログインに係る情報からこれらの投稿をした者を特定することは困難であって、あえて本件ログイン①に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情があるといえる。
したがって、本件ログイン①は、本件投稿との関係で、施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるというべきである。
他方で、本件ログイン②~⑧は、本件ログイン①と比べ、本件投稿と時間的に近接していない。そして、上告人は本件ログイン①に係る発信者情報を保有しており、これに加えて、あえて本件ログイン②~⑧に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情はうかがわれない。
したがって、本件ログイン②~⑧が、本件投稿との関係で、施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるということはできない。
(侵害関連通信)
第五条 法第五条第三項の総務省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。
(略)
二 侵害情報の発信者が前号の契約に係る特定電気通信役務を利用し得る状態にするために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態にするための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をした者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信
まとめ
プロバイダ責任制限法の改正により発信者情報開示の対象範囲が整理されましたが、本判決では、権利侵害があるとされる投稿が改正前であるものの、その開示に当たり改正後の条文が適用されるのか否かがまず問題となり、これについては、改正後の条文が適用されることを明らかにしました。
その上で、本件各ログイン情報が、改正後法の施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」といえるかどうかが問題となり、原則として「侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信」がこれに当たり、そのほか「あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情がある」ときにも上記関連性があるといえるとの判断枠組みを初めて示しました。
情報技術の話もあいまって、なかなか難解な印象を持たれた方も多いかと思います。
とはいえ、冒頭で述べたとおり、これからますます存在感を強めていくこと必至のIT分野。
IT×法律という難解な場面でも弁護士の関与を必要とする場合があります。
ITやSNSなどでお困りの際には、是非弁護士にご相談ください。