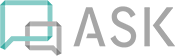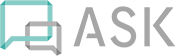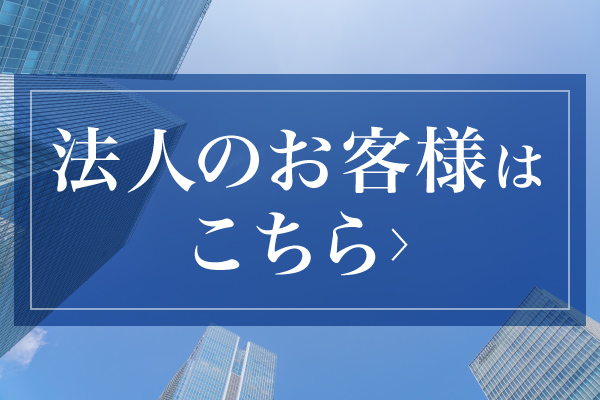高速道路の料金所に止まることなく、スムーズに通過できるETC。レジャー時に、通勤時にと、皆さんも利用することが多いことでしょう。そんなとき、誰名義のETCカードを使っていますか?ご家族、ご親族名義のETCカードを利用していることも多いのではないでしょうか。それ、電子計算機使用詐欺罪に当たってしまうかも!?
大阪地裁令和6年5月8日判決の事案
被告人は、AからCの3名です。Aは暴力団関係者、BはAの知人、そしてCはAの弟という人物相関です。
そして、AとBが乗車する車(Cは乗車せず)に登載されたETC車載器に、C名義のETCカードを挿入した状態で、
- 令和4年11月8日午前6時41分から同日午前6時50分頃までの間、m料金所入口から高速道路に進入し、n料金所出口まで走行
- 同年12月2日午前7時5分頃から同日7時16分までの間、o料金所入口から高速道路に進入し、p料金所出口まで走行
しました。そして、このいずれの場合にも、高速料金はETC割引が適用されたものでした。①では770円相当の割引、②では630円相当の割引を受けています。
この各行為が、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)に該当するとされたのです。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246の2)とは、どんな犯罪類型か。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条(註:詐欺罪)に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
通常の詐欺罪は、平たく言えば、人をだまして財物や財産的利益を得る犯罪行為です。
他方、この電子計算機使用詐欺罪は、人をだますのではなく、「人の事務処理に使用する電子計算機」(例:ATMや業務に使用するパソコンなど)に「虚偽の情報」等を与えたり、「財産権の得喪」等に「係る虚偽の電磁的記録」(例:オンラインシステム上の預金口座の元帳ファイルにある預金残高の情報)を供用したりことで、財産上の利益を得ることが禁止された行為となります。
電子計算機使用詐欺罪はそれまでの詐欺罪では処罰できない行為を対象とするために設けられた規定
電子計算機使用詐欺罪は、今から約40年前に、それまでの詐欺罪では捕捉できないコンピュータ絡みの不正な利得行為を処罰されるために設けられました。そのため、「前条に規定するもののほか」と規定され、通常の詐欺罪(刑法246条)では処罰することができない場合に初めてその適用可能性が問われる規定です。
どのような争点だったか
ETCカードの家族や親族間の貸し借りは、よく行われているようにも思えます。例えば、車をよく利用する甲さんがETCカードを持っていて、甲さんの配偶者でサンデードライバーの乙さんという夫婦がいたとします。そして、乙さんが、週末に、甲さん名義のETCカードをETC車載器に挿入し、高速に乗ってちょっと遠くのアウトレットでお買い物…なんてことは世の中にあふれていそうです。今回のAが暴力団関係者であったとしても、行為を客観的に観察すると、一般的に行われていそうな態様です。その属性のみをもって悪いことだと決めつけてしまうのは早計です。
弁護人の主張
一見して、よくありそうな事柄ですので、弁護人も次のように反論して、無罪を主張していました。
- ・被告人らは、「虚偽の情報」を与えていない
- ・「財産上不法の利益」を受けていない
- ・故意がなく、不法領得の意思もない
① について
カード名義人が同乗しているという情報までは要求されていない
虚偽の情報を与えていないという弁護人の主張について、少し見ていきます。
ETCシステムは、道路整備特別措置法や同施行規則等の文言を前提とすると、料金の徴収のために必要なその通行に関する情報を、当該料金を納付するために通行車をして記録させることにあるから、ETCカード名義人の情報が要求されるのみであって、カード名義人が同乗しているという情報までは要求されていないと主張しました。
「虚偽の情報」といえるには、判断の基礎となる重要な事項についての「虚偽」でなければならない
D高速社にとって「通過車両内にETCカード名義人が乗車している」との事情は上記の重要な事項ではないとも主張しました。
AとCの関係からすれば、Cは高速料金の支払を免れられない立場にある
仮にETCシステムにおける「通過車両内にETCカード名義人が乗車している」との事情が重要な事項に当たるとしても、クレジットカードの会員規約では、クレジットカードの紛失・盗難の事実をカード会社にすみやかに届け出る等の所定の手続をとった場合であっても、家族等の会員の関係者によって使用された場合には会員の支払は免除されないとされているから(会員規約15条2項)、会員の関係者は会員と同視できるとされているのであって、これはETCカードにもあてはまるとして、本件ETCカードの名義人である被告人Cの極めて身近な関係者である被告人Aによる本件ETCカードの使用は被告人Cによる使用と同視できると主張しました。
② について
平穏にETCレーンを通過した場合には現金払いとの差額を観念できないなどと主張しました。
③ について
故意がない
故意とは、犯罪事実を認識し、そこから生じる結果の発生を容認した状態をいいます。刑法上の犯罪については、基本的に故意がなければ処罰の対象とはならないのが原則です(刑法38条1項本文)。ちなみに、この原則に対する例外の代表例が、過失犯です。
本件の弁護人は、被告人らは電子計算機使用詐欺罪が成立することを知らなかったと主張しました。
不法領得の意思がない
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用、処分する意思を意味し、詐欺罪をはじめ、窃盗罪など財産に関する罪について故意のほかに必要とされる主観的な要件です。
本件の弁護人は、被告人Aは、ETCレーンを利用するとスムーズに高速道路に流入できるから本件ETCカードを使用したのであって、現金払いとの差額を得るためではないと主張しました。
裁判所の判断
上記のように反論した弁護人の主張に対し、いずれもその反論を認めず、電子計算機使用詐欺罪の成立を肯定しました。弁護人が反論し争点となった点について、裁判所がどのように判断したか見ていきましょう。
「虚偽の情報」を与えていないというポイントについて
ETCカード名義人以外の者が使用することを禁止していると判断
裁判所は、D高速社の営業規則やETCカードの主たるクレジットカードの規約等を解釈し、本件ETCカードが主たるカードであるクレジットカードの決済機能を利用するものである以上(ETC利用規定2条2項)、本件ETCカードもクレジットカードと同様に、カード名義人の個別的な信用を基礎として貸与されていることによるものと考えられるから、ETCカードを使用する有料道路を管理し、利用料金を徴収するD高速社及び本件ETCカードの発行元であるEファイナンスのいずれも、本件ETCカードをカード名義人以外の者が使用することを禁止していることは明らかだと判断しました。
ETCカードを貸与されたものが電子決済することが重要な前提とされている
ETCシステムにおいては、クレジットカードに付帯するETCカードを使用する場合には、所定の審査を経てクレジットカードの発行を受け、ETCカードの貸与を受けた者との間でのみ電子決済をすることが重要な前提とされているといえる。そうすると、カード名義人である被告人Cが同乗していないのに、被告人A及び被告人Bが本件ETCカードを使用したことは、ETCシステムで予定されている事務処理の目的に照らして真実に反する。
結論
「虚偽の情報」を与えたといえる。
弁護人の反論に対する裁判所の判断
カード名義人が同乗しているという情報までは要求されていない点について
ETCシステムは電子決済の一種であり、ETCカードがクレジットカードと結びついており、クレジットカードが名義人以外の者による使用を許さないものである以上、このような契約の内容を無視して、名義人以外の者がETCカードを使用することを許しているとは考えられないとして、反論を認めませんでした。
「虚偽の情報」といえるには、判断の基礎となる重要な事項についての「虚偽」でなければならないとの点について
- ・ETCレーンを通過する際、カード名義人の乗車を要求することは、ETCシステムの利便性向上に反しない。ETCシステムはカード名義人の乗車を前提としている。
- ・ETCカードの利用規則が分かりにくいとの指摘に対しては、ETCカードがクレジットカードと同様に他人への貸与が禁止されていることが明確に示されているため、理解しやすい。
- ・D高速社がETCカードの不正使用についての広報活動や実態調査をしていないとの批判に対して、広報活動の有無は不正通行の悪質性や広がり、経済合理性を考慮して決定すべきであり、活動がなかったからといって関心がないとはいえない。
- ・ETCカード名義人の乗車に関する錯誤がなければ通過させなかったという因果関係について、ETCシステムがカード名義人の乗車を前提としているため、錯誤がなければ通過させなかったと考えるべき。
- ・道路交通法改正により遠隔操縦が認められたが、これは通常の車両におけるETCカードの利用規則に影響を与えない。遠隔操縦の場合の規定はまだ議論中であり、現行の規則が無意味化しているとはいえない。
といった点を挙げ、D高速社にとって「通過車両内にETCカード名義人が乗車している」との事情が「虚偽の情報」の判断の基礎となる重要な事項ではないと評することはできないとして、弁護人の反論を認めませんでした。
財産上不法の利益を得ていないとの点について
正規料金との差額が生じている以上、「財産上不法の利益」を得たものとして、弁護人の反論を認めませんでした。
故意や不法領得の意思がないとの点について
故意の点について
被告人らは、被告人Cが同乗していない状態で、被告人A及び被告人Bが被告人C名義の本件ETCカードを利用して、ETCレーンを通過したという事実を認識・認容しているから、故意に欠けるところはないとして、故意を認めました。
不法領得の意思の点について
ETCカードを利用すれば割引制度が適用されることは公知の事実であり、被告人らがこれを知らなかったという事情も見当たらないので、被告人らに不法領得の意思が認められることも十分に肯定することができるとして、不法領得の意思を認めました。
結論
以上から、裁判所は、被告人らに、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めました。
プラスαとしての「可罰的違法性」についての議論
刑法学上、犯罪とは、構成要件に該当する違法有責な行為と定義されます。構成要件、すなわち、殺人罪や窃盗罪といった刑法典に書かれた犯罪類型に該当すれば、「違法性」が推定されるのですが、例えばティッシュ1枚を盗んだといったように、時として、罰するほどの違法性がないケースもあります。
本件でも、被告人Cは、被告人Aらが本件ETCカードを使用することについて了解していたので、このような実態と、「ETCカードの名義人が同乗する」との情報との違いに、処罰に値するだけの「虚偽」性が認められるのかといった疑問が生じます。この点について、裁判所は、次のように述べて、罰するほどの違法性が“ある”と判断しています。
過去の判例でカードの名義人の同意の有無は詐欺罪の成否に影響しないとされていること
クレジットカードは、名義人の承諾の有無にかかわらず、名義人でない者が使用することを許しておらず(会員規約3条4項、5項等)、名義人になりすまして使用した場合には詐欺の罪責を負うものと解される(最高裁平成16年2月9日第2小法廷決定・刑集58巻2号89頁参照)。
AとBは、本件のような態様を繰り返していたこと
関係証拠によれば、被告人A及び被告人Bは、被告人Cが同乗しない状態で本件ETCカードを頻繁に使用していたことが認められ、本件は、そのような常習的な行為の一環といえる。
本件のような態様は、暴力団排除条項を潜脱するものであること
本件ETCカードの主たるカードであるクレジットカードの会員規約29条には暴力団排除条項が規定されており、暴力団員にはクレジットカードを発行しないこととされているのであるから、クレジットカードに付帯するETCカードも暴力団員に発行されないはずであることは明らかである。ところが、被告人Cは、本件ETCカードと別のETCカードの発行を受ける一方、暴力団員である被告人Aと被告人Bに本件ETCカードを使用させ、本件ETCカードの利用料金については被告人Aが被告人Cに金員を渡し、被告人Cの口座から引き落とすことによって支払っていた。このような本件ETCカードの使用方法は、暴力団員との取引を拒絶する暴力団排除条項を潜脱するものである。
考察
裁判所は、以上のようにして、被告人ら3名に有罪判決を下しました。みなさんはこれを妥当だと思いますか?
ETCを利用する際、ETCカードの名義人が同乗していないといけないと知っている人はどれほどの数いるでしょうか。また、家族や親族間でETCカードを融通することは、それほど稀な行為でしょうか。レンタカーではETCカードがレンタルできるのに、家族間で貸し借りをして、カードの名義人が同乗していないことで今回の罪が成立することは果たしてバランスがとれているといえるのでしょうか。
また、暴力団には社会全体として対抗しなければなりませんが、一方で、今回のように他の利用者と変わりのない利用方法でETCを利用した暴力団関係者をその属性のみをもって処罰することは妥当でしょうか。
いろいろな角度から、本判決の持つ意味を考えてみる必要があるかもしれません。